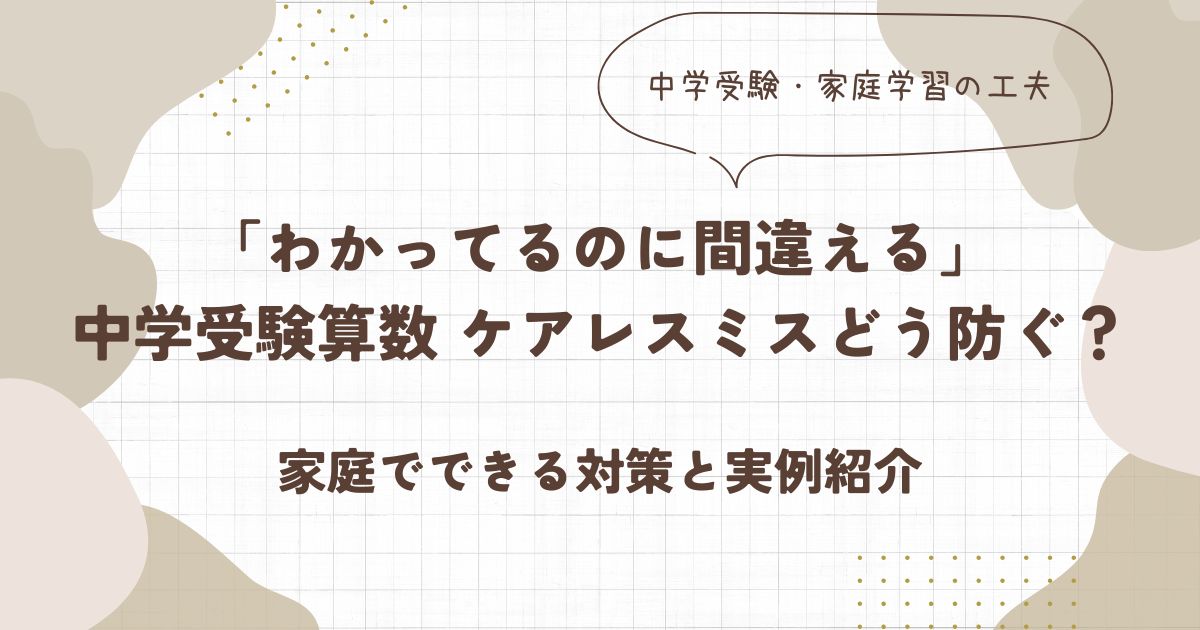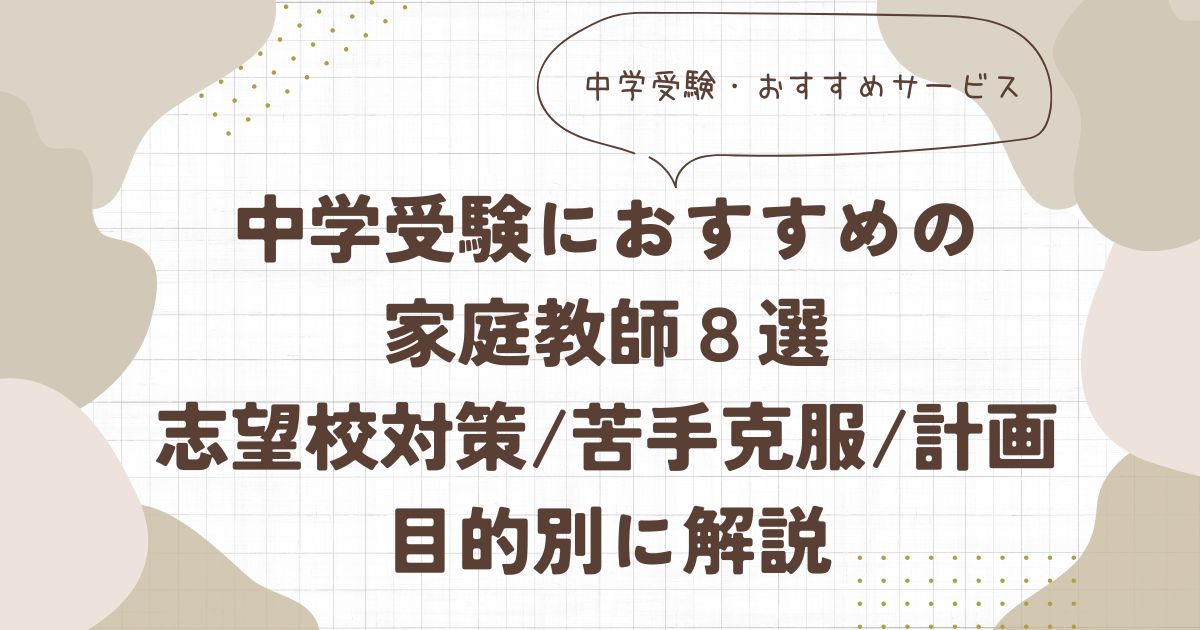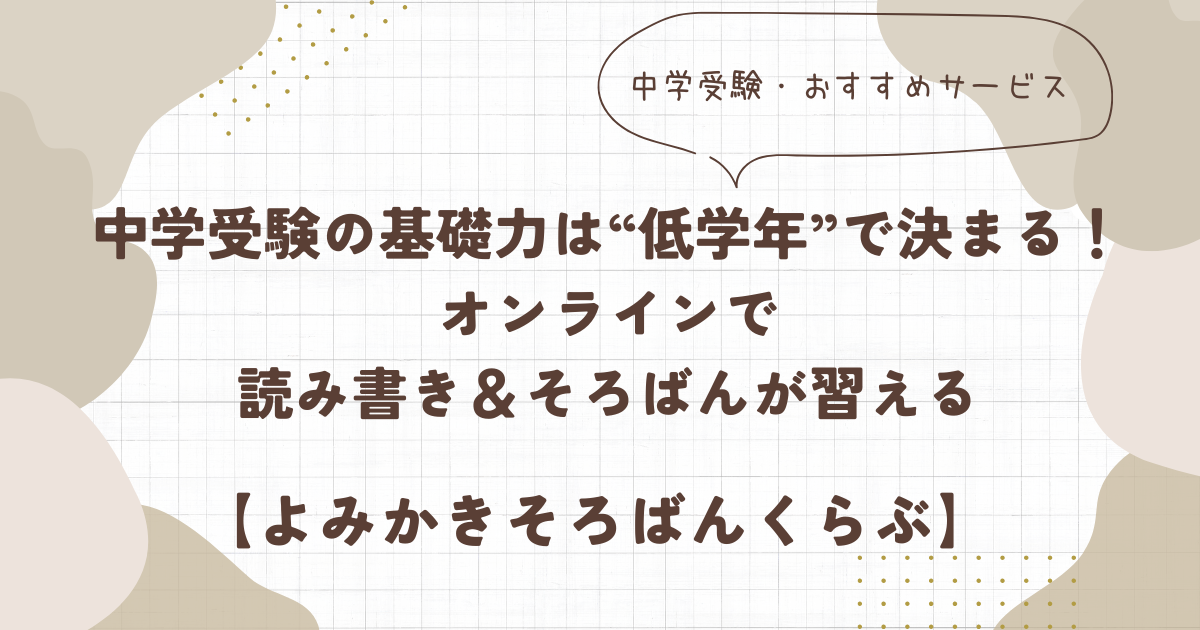はじめにーーー
ケアレスミスで落とす点がもったいない!
中学受験の算数で一番悔しいのが、「わかっていたのに間違えた問題」ではないでしょうか。
我が家の小5の息子も、まさにそれです。
模試や通信教材のテストで、「計算さえ合っていれば正解」という問題をいくつも逃していました。
しかも原因は「難しい問題」ではなく、
- 四則計算の符号ミス、単純な計算ミス
- ノートに写すときの数字の書き間違い
- 最後の計算を忘れる
- ノートの数字が汚くて、自分でも読み違える
- 小数点のつけ忘れ
- 問題をよく読んでいない
という、ケアレスミス、凡ミスの温床のような状態でした。
なぜケアレスミスはなくならないのか
子どもが「できるはずなのに間違える」ことが多いのは、実は実力不足ではなく、むしろ習慣と環境の問題だからなのだそう。
核となる原因は以下の2つです。
● 注意力の揺らぎ
短時間の集中が途切れると、ほんの少しのズレがミスにつながります。例えば「いつも通り」解いていたはずが、途中で気がそらされて数字を見間違える。これは“実力”ではなく“集中が切れた一瞬”です。
● 焦りからくる手抜き動作
受験勉強をしている以上、時間との戦いでもあります。でも「早く解こう」と思えば思うほど、式を飛ばしたり、ノートを省略したりしてケアレスミスが出やすくなります。
つまり、ケアレスミスは「まだ実力が足りないから」ではなく、「習慣的に見直す仕組みがない」「集中を保つ環境が整っていない」から起きるのです。
よくあるケアレスミスのパターン5つ
次に、実際によく見られるミスのパターンを紹介します。お子さんがどれに当てはまるかチェックしてみてください。
- 計算を急ぐ(途中式を省略)
例)「7×8=」だと思い瞬時に計算したが、実際は「8×6=」。頭の中で数字を取り違ってしまったが(そういうことがあるのです)、途中式を省略したためミスに気づかずそのまま。 - 問題文を最後まで読まない
例)「何分で…」という速さの問題を「何時間で…」と勝手に読み替えて式を立ててしまう。「文末の“分”を“時間”と読み飛ばした」 - 単位や符号を見落とす、間違える
例)「−5 m」の意味を“5 m”と捉えてしまった。あるいは「㎝」と「m」を混同してしまった。 - 見直しを形式的にしてしまう
例)「答えが〇だからOK」と思い込んで、途中式や単位までチェックせずに終了。 - 集中力が切れる
例)模試の終盤になると字が乱れ、筆算が雑になり、数字が見づらくなりミス連発。「60分を超えると集中が切れた」
ミスを減らす6つの習慣
では、これらのミスを減らすために、我が家で実践して効果があった5つの習慣をご紹介します。
- 「1行1計算」を徹底する
途中式を省略せず、必ず1行1つの計算を書かせる習慣をつけました。
書くことで「省略しない」意識が生まれます。
✕36÷4×3=9×3=27
◯36÷4×3=
9×3=
27
途中式を省略してしまうと、頭で起きた“取り違え”を後から検証できません。
必ず途中式を書き、逆算や概算でチェックする習慣をつけています。 - 最後に「単位だけ確認」時間を取る
答えを書き終えたら、必ず30秒だけ単位チェック。
問題文をもう一度見て「m/㎜/cm」「時間/分」を確認します。 - 問題文で「なにを聞かれているのか」をチェックする
文章題では、計算力よりも「何を求める問題か」を読み取る力が試されます。 たとえば、まわりの長さを聞かれているのに、面積を求めてしまう。あるいは「AとBの差」を聞かれているのに、「AとBの合計」を出してしまう——こうしたミスは、実力ではなく確認不足から起こります。
我が家では、問題文の最後に赤ペンで「求めるもの」に線を引く習慣をつけました。
「〇〇の長さ」「合計」「速さ」など、“ゴールを明確にしてから”計算に入るようにするだけで、ケアレスミスは確実に減ります。 - ミスノートをつける
記録を可視化することで、自分のミスの“傾向”がわかります。
・日付・教材・問題名
・ミス内容(例えば、写し間違い)
・原因分析
・次に気をつけること
・再チャレンジ結果(〇をつける)
こうして蓄積すると、「毎回同じミス」が明らかになります。 - 模試やテスト後に“ミス分析タイム”を作る
模試やテストの結果が返ってきたら、親子で時間をとり、「どういうミスがあったか」「次回何を省略せずにやるか」を話し合います。 - 「焦らない」練習を意識的に行う
制限時間を少しゆるめに設定して練習を開始。
時間を少し余って終えると、「丁寧に確認する余裕」が生まれます。
その感覚を模試本番でも再現するようにしています。
我が家のミスノート具体例
実際に我が家で使っているミスノートの内容をご紹介します。
日付: 10月31日
教材: Z会中学受験コース 算数 小5
ミス内容: 問題文の速度が「分/時」だったのに「分/分」と読み替えて式を立てた → 答えが現実離れした値に。
原因分析: 問題文を読み飛ばして「分」を「時」と読み取ってしまった。速度・時間・距離の単位をいつも「時」で考えていた。
次に気をつけること: 問題文に「分/時」や「時間/分」があるかをまず確認。「/」の後に来る単位を赤線で囲む。答えを概算で確認する。明らかに違う場合は答えを疑う。
再チャレンジ: 同じ単元の同じような別問題に取り組む→ 正解。
1ページにまとめることで、後で見返したときに「この月・この分野でこのミスが多かったな」という傾向が可視化されて、気をつけることが明確になります。
ケアレスミス対策におすすめの教材・サービス
ケアレスミスを大幅に減らせるのは、習慣化できる教材・サポート体制がある学習サービスです。
- Z会 中学受験コース:毎日練習ブックが基礎力&確認力を育て、テストの添削でミス傾向を指摘してくれます。
- スタディサプリ 小学講座:映像+演習で「なぜミスが起きるか」を視覚的に理解できます。
- トウコベ(家庭教師):マンツーマンで「ノートの書き方」「途中式の位置」など細かいチェックが可能です。
👉 Z会公式ページはこちら
👉 スタディサプリ小学講座![]() 👉 「トウコベ」まずは無料相談
👉 「トウコベ」まずは無料相談 ![]()
まとめ:ケアレスミスは「性格」ではなく「習慣」で変わる
以前は「集中力が足りないんだろうな」と思っていました。
でも実際は、「正しい振り返り方」を知らなかっただけ。
ミスノートで自分の傾向を知り、毎日の練習を丁寧に積み上げることで、確実に“ミスの数”は減っていきました。
ケアレスミスは「才能」ではなく、「仕組み」で防げます。
今日から、ミスノートの作成をおすすめします!